「
標準語」という言葉は、どこからやって生まれたのでしょうか?
「
標準語」とは、「
一国で、規範的・理想的なものとして認められている。共通の言葉」(岩波国語辞典)ということです。
「
標準語」は、
東京地方の言葉をもとにして、当時の政府が様々な方言を1つにしようとした結果の言葉です。
江戸時代から明治維新(明治時代)に移り変わる時に生み出されたために…(O.O;) (o。o;)
たとえば、「
こら こら!」は、薩摩弁で「
ちょっと ちょっと!」という意味です。当時、「
警察官」になった人の多くが
薩摩(鹿児島)出身だったために、「ちょっと」がなぜか「怒られている」ように感じてしまったようです。
標準語だと思っていても…普段使っていそうな言葉の中に方言が使われているのですよ!
東京のど真ん中は、めちゃ うざい っしょ
けど、あすこの3階 に 行ったら、
まったりしてられん じゃん。 |
さて、その実態は…
(関西) (関西) (多摩) (北海道)
東京の
ど真ん中は、
めちゃ うざい っしょ
(関西) (関東) (九州) (九州) (関西)
けど、
あすこの
3階 に 行っ
たら、
さんかい→本来はさんがい
(関西) (関東) (山梨? 横浜? 三河?)
まったりしてられ
ん じゃん。
それを標準語で、言い表すと… (O.O;) (o。o;)
「
ハイブリッド」の意味を分かっていますか。(・_・>)
自動車のことではありません。
日本語を表すには、「
漢字」以外にも「
カタカナ」や「
ひらがな」があります。
漢字を使っている言葉として、日本語と中国語があります。
でも中国語には「漢字」しかないのです。(・_・)
外来語も全て「漢字」です (・_・>)
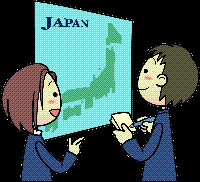
もし、日本語に「カタカナ」や「ひらがな」がなかったらどうでしょうか…
日本語で、外来語を表すのに「カタカナ」はとても都合の良い方法だったのです。
日本に漢字が伝来して以来、「公文書」は漢字で表していました。
「カタカナ」や「ひらがな」は、漢字の一部を変化させて作り出したものだそうです。
平安時代の女性が使い始めたのが、ご存じ「ひらがな」です。この「ひらがな」を使って、あの「平安王朝文化」が開花しました。
江戸時代の末に大量に入り込んだ西洋文明にすぐ対応できたのは、この「カタカナ」があったからです。
様々な外来語を理解するのに、とても役立ったわけです。
「
さぼる」は、フランス語に由来する「
サボタージュ」sabotage(仕事をなまけてやらない…)を日本語に取り入れたものです。
日本語ってすばらしいですね。 (^○^)
では、答えです。
「ハイブリッド」(hybrid)とは… 「複数の方式を組み合わせる」ということです。
「ハイブリッドカー」となると、… 「電気モーター」と「ガソリンエンジン」などを組み合わせた車という意味になります。
「カタカナ語」は大変便利ですが、その意味を正しく知って使えるようにしましょう。(-o-)/