2月22日(火)にニュージーランドで大きな地震がありました。
震源は、ニージーランド 南島 大都市「クライストチャーチ」付近で、
地震の規模(
マグニチュード)は、
6.3でしたが、
震源の深さが5キロメートルだったため、
ゆれの大きさ(震度)が大きくなり、建物が大きくこわれて、多くの死んだ人や連絡の取れない人が、出ているそうです。
|

|

|
|
地震が発生しやすいところ
|
ニュージーランドのプレート
|
図のように、ニュージーランドは、「
太平洋プレート」と「
オーストラリアプレート」(オーストラリアが乗っているプレート)が、ぶつかり合っている地域です。
1年生の理科の学習で、地震が起こる原因は…
(1) プレートどうしが直接ぶつかり合う 「
海溝型地震」
(2) プレートの動きによって生じた大きな力によって、すでに傷ついている断層のずれによる 「
内陸型地震」
の2つがあることを学びました。 (・。・)
今回の地震は、すでに傷ついている断層(活断層)のずれによる
都市直下型の「
内陸型地震」です。
また、去年 9月にすぐ近くで起きた地震 <マグニチュード(M) 7.0>の余震(?)ではないかと…言われています。
日本でもいつ起こるか分からない地震です。1月に行った「避難訓練」と「防災教室」で学んだことを生かして生活しましょう。
9月も第2週に入り、授業のリズムも元に戻ってきました。理科室での授業も活発に行われています。
また、協力し合いながら観察・実験を進めることができています。( ^)o(^ )
それぞれの学年での実験の様子をごらんになって下さい。o(^o^)o
 |
|
1年・凸レンズのつくる像
|
 |
|
2年・磁石のつくる磁界
|
 |
|
3年・細胞分裂の観察
|
「夏休み」も終わりです。(:_;)
「夏」といえば、「すいか(西瓜)」ではなくて、「蝉(せみ)」です。
「夏」には欠かせない「蝉の鳴き声」ですが…(・_・>)
蝉(せみ)の一生のほとんどは、土の中で生活しています。種類によって違いはありますが、7年くらいの一生の中で、地上で生活するのは、一週間(7日)くらいしかありません。
地上に出た幼虫は、薄暗い朝に脱皮して成虫になります。その7日間で、相手を見つけて「卵」(子)を残して、一生を終えます。
そのわずか7日の間を、蝉(せみ)は地上の「美しい風景」をみて、一生懸命に生活しているのです。(‥、)
何か…はかないですね。(・_・)
 |
|
蝉の脱けがら
|
「蝉の脱けがら」を見つけると、ふと、そう思うことがあります。
皆さんは、この地上の「美しい風景」をみて、生活していますか!
さぁー、2学期です。
自分が頑張れるところをたくさん見つけて、活躍の場面をたくさんつくって下さい。ヾ(^v^)k
8月も10日が過ぎました。一番暑い時期も?!まもなく一段落…
使っていない照明をこまめに消して、そしてエアコンの温度も1℃上げましょう。
扇風機を使った、省エネルギーに取り組むのにいい時期です。
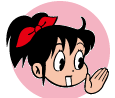
でん子ちゃんも喜びますよ